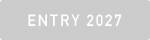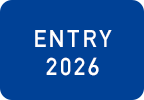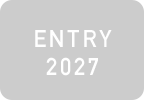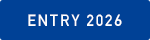

- CAREER STORY
- エンジニアリング
「新しいこと」に挑戦し、
チームで試練を乗り越える。
- 酒井 浩太郎
- 青海エンジニアリング部 設計課 課長
1997年入社
工学部 機械工学科卒
※社員の所属部署・記事内容は取材当時のものです
キャリアパス
- 1997年
- 大船工場 施設部
- 2003年
- 本社 樹脂加工事業部 樹脂加工事業企画部 企画管理課
- 2004年
- 本社 建材・産業資材事業部 樹脂加工事業企画部 企画管理課
- 2005年
- 大船工場 大船エンジニアリング部 設備課
- 2006年
- 千葉工場 千葉エンジニアリング部 設備保全課
- 2009年
- 大船工場 大船エンジニアリング部 設備課
- 2013年
- 大船工場 大船エンジニアリング部 設備課[課長代理]
- 2014年
- 大船工場 大船エンジニアリング部 設備課[課長]
- 2015年
- 青海工場 青海エンジニアリング部 無機設備課[課長]
プロローグ
機械工学科で流体を学んでいた酒井は、読んでいた本で目に入った「メーカーは創造主である」という言葉に感銘を受け、就職活動ではメーカーを志望する。業種業態に特にこだわりはなかった。
「何に向いているかわからないし、とにかく新しいことがしたかった。化学メーカーに就職が決まったのも、巡り合わせでした」
入社後に配属されたのは大船工場。早く独り立ちしたいという一心で、ときに空回りしながらも目の前の仕事に一生懸命に取り組んだ。

STEP 1:24歳初めての主担当案件で
仕事の厳しさを実感する
入社3年目、酒井は初めて主担当として仕事を任されることになった。内容はフィルムの押出し機の能力増強工事だった。この初めての主担当の案件は、いまも酒井の脳裏に焼き付いている。
まず各種設備の能力決定をし、設備内容に基づいて詳細な設計を実施する。そしてその設計図面に基づいて工事が行われるが、製品確保のため生産ラインを止めずに行う必要があった。しかし当時、経験が浅かったこともあり、十分なシミュレーションができておらず、工事がスムーズに進まなかった。
「どの順番で協力会社に作業依頼するか、重機や資材の配置から、現場作業の動線をどうつくるかまで、十分に段取りをしたつもりでしたが、まったく足りていませんでした」
工程を詰め込みすぎてしまい、協力会社に迷惑を掛けることになった。工事が上手くいくかどうかは、自らの段取り次第であることを身をもって経験した。
さらに新規設備を設置後にも課題に直面することになる。
「2枚のフィルムを同時に製造する工程で、2枚の厚みがどうしてもそろいませんでした。調査の結果、付近の設備から出る輻射熱が影響していることがわかりました。本来なら設計段階で気づくべきことでしたが、当時の私には見抜きようもありませんでした」
原因を特定した後は、さまざまな方に協力してもらい、断熱工事を追加してようやく目標の生産能力の増強を達成することができた。
初仕事での苦い経験は、酒井にとって忘れがたい大きな教訓となっているという。

STEP 2:37歳海外プロジェクトで
チームの力を知る
2011年、シンガポールに新工場を建設するプロジェクトが立ち上がり、主担当として酒井が抜擢された。初の海外プロジェクトであり、新工場立ち上げに携わるのも初めてのことだった。新工場設立の目的は、大船工場の主力生産品目の海外展開であり、同工場の製造プロセスを熟知するスタッフの力が必要とされたのである。
「海外への生産展開がテーマだったので、大船工場の社員に不安を与える可能性があり、計画段階ではとても気を遣いました。
それでも前向きに取り組むことでメンバーの意識を前向きにしていくことができました」
デンカにはシンガポールに3つの工場があったため、当時の建設に関わった先輩や、現地駐在の方やスタッフから酒井は多くのアドバイスをもらい、プロジェクトを進捗させた。建設計画がまとまってからは、製造・研究・エンジニアリング部のメンバーが加わり、大きなチームとなっていく。
「大きな規模になればなるほど、メンバーの力を活かすことが大事になります。メンバーを信頼して実務を任せることで、徐々にチーム全体の結束が強くなっていくのを感じました」
2013年に、新工場は無事完成する。酒井はこのプロジェクトを通じてマネジメントを通じて実現する「チームの力」の重要性を実感した。

STEP 3:41歳毎日が「試練」の連続
2015年、酒井は課長として青海工場のエンジニアリング部の設計課へ異動となる。辞令はまったくの予想外だった。まず、青海工場は無機化学を中心としたプラントが約半分を占めており、これまで有機化学の樹脂加工を主に手が掛けてきた酒井にとっては未知の分野だった。
「青海は水力発電所や鉱山などもあるのですが、特に山での土木工事はまったくの未経験でした。今も先輩や部下を含め、多くの方に教えを請いながら仕事をしています」
「たとえばトンネル一つ掘るにしても、地質調査など工程が多岐にわたります。知れば知るほど、難しさを感じます」
そんななかでも酒井は課長としてチームを率いねばならない。15人の部下をマネジメントし、日々多くの業務を滞りなく進行させる一方で、ベテランの技術を若手に継承させなければチームとしての成長が止まってしまう。
「毎日が試練ですね」と苦笑いする酒井は、マネジメントをする上で「自主性」を意識していると語る。
「強制されている、やらされている、と思うと、自分の挙げた成果がどこか他人事のように映ります。自分の頭で考え、自分の力で成し遂げた手応えを感じてほしい。時間はかかりますが、長い目で成長を見守るように心掛けています」
FUTUREメーカーは創造主であるべき
「新しいことをしたい」と飛び込んだ酒井にとって、これまでのステップはまさにチャレンジの連続だった。チャレンジを支えたのは、「人とのつながり」だったと酒井は振り返る。
「いわゆる『技術屋』に憧れてメーカーを選んだのですが、この仕事は人に始まり人に終わるのだと今は思います。お世話になった方、助けてくれた方は数え切れないほど。人とのつながりが今のキャリアをつくっているんです」
酒井のチャレンジはまだ終わらない。「他社に負けない新しい製品をつくりたい」と酒井は未来を見据える。
「斬新な製品を生み出すには、先端技術やビジネスモデルなど、社外の情報を積極的に吸収する必要があります。客観的な視点で『あるべきもの』を探りたい。これぞメーカーの醍醐味ではないでしょうか」