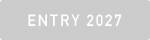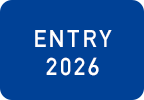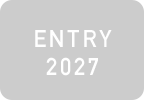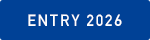

- JOB REVIEW
- 資源
デンカの競争力の源、
石灰石を安定供給する。
- 鎌本 隼平
- 青海工場 資源部
2009年入社
工学研究科 環境プロセス工学科専攻修了
※社員の所属部署・記事内容は取材当時のものです
カーバイド製造部門から資源部へ突然の異動
入社後の配属先は、青海工場の無機部。カーバイドの製造スタッフとして、プラントの設備改善や省エネの実行に携わった。大学院で化学工学を専攻してきた鎌本にとっては、ほぼ希望通りの配属だった。
工場での経験を一つひとつ順調に積み上げていた鎌本に突然の辞令が下りたのは、入社4年目の1月のことだった。異動先は青海工場資源部原石課採掘係。「自らの持つ専門性をさらに高めたい」という思いで入社した鎌本にとって、この異動は青天の霹靂だった。
「正直なところ、自分のバックグラウンドとほぼ関連しない部署への異動だったので、不安も大きかったです。ただ、ここでの経験は間違いなく自分のキャリアにプラスになると思い、前向きに捉えることにしました」
資源部のミッションは、デンカが所有する鉱山から石灰石を採掘し、工場へ安定的に供給すること。そのなかで、鎌本が担当するのは、石灰石の採掘計画の立案や、採掘にともなう許可申請書類の作成だ。
毎日約7,000tの石灰石を確実に採掘するためには、細部にわたって正しく立てられた採掘計画が必要不可欠だ。採掘が進めば、それにともなって現場の地形も変わるため、3カ月ごとに計画を更新しなければならない。鎌本は基本的にこの仕事を一人で担当する。
「デンカの製品にとってなくてはならない原料である石灰石を安定供給するための計画ですから、責任は重大。異動からもうすぐ丸2年(※取材当時)経ちますが、まだまだ勉強しなければならないことがたくさんありますね」

現場と二人三脚で採掘計画を立てる
採掘計画を立てるには、GPSを駆使して採掘現場の面積を測定し、実際に地形図やベンチのレイアウトを描いて、鉱量計算を行うことから始める。日本一の大きさを誇る油圧ショベルやダンプトラックが、現場に効率よく出入りできるような道筋をどうつくるかなどの作業性も同時に検討する。
「迷ったときは、現場の主任に相談します。採掘現場に出入りするのは、218tもの石灰石を一度に積み込むことができるダンプトラック。
こうした重機を安全に無駄なく動かして、採掘を実行するには、現場の意見をことあるごとに確認するなど、積極的にコミュニケーションを取る姿勢が必要です」
また、資源部に配属後、鎌本が思った以上に苦労したのが、各種許可申請書の作成だった。関接部門と協力して申請書類を提出する他の製造部門と違い、資源部は単独で行政機関とのやりとりを行う。
山にトンネルを掘るなど、新たな開発が必要になった際に、実際にどのように工事を行うのかという申請書を経済産業省と県へ提出する。計画の具体的な進め方を記載したものから、地形図や安全対策について説明する内容のものまで、量も種類も多い。
「まずは内容を理解するところから始めなくてはならない申請書類も多く、予想以上に苦労しました」

新しい鉱山の開発準備という貴重な経験
現在、資源部が採掘を進めているのは、西山と呼ばれる西側の現場だ。採掘は鉱山の壁に傾斜をつけながら行われるため、掘れば掘るほど採掘可能な範囲が狭くなる。西山の採掘現場も、すでにかなり狭くなっている。そこで来春からは、新たに東山から採掘を始める開発計画が進行中である。現在は、石灰石を山の下に降ろすための立坑、立坑の下から工場まで石灰石を運び込むベルトコンベアなどの設備は完成し、試運転中である。
また、東山の地形に合わせた、穿孔機や油圧ショベル、ダンプトラックなどの重機も新しく揃える必要がある。
「取り扱う重機は数千万~数億円という世界。これらの重機をどれくらい揃えるかを考えるのも私の仕事。大きなお金を動かすことになるので、失敗は許されません。コストや環境も意識しながら、採掘に最適な環境を整える。頭は使いますが、面白い仕事ですね」
今後は、これまでは採掘しても工場に運ぶことはなかった低品位の石灰石も有効利用し、限りある資源を無駄にしない操業ができるようになりたいと語る鎌本。専門外の資源部への配属から5年弱、一歩一歩前に進みながら知識と経験を積み上げてきた。今後も新たな採掘現場の開発という貴重な経験を通じ、さらなる飛躍を遂げるだろう。
一日の仕事の流れ
- 06:40
- 起床
- 07:40
- 自宅を出発 通勤は独身寮から自動車で通勤。
- 08:10
- 会社に到着
- 08:30
- ミーティング
- 09:00
- 坑廃水のサンプリング及び分析 坑廃水が法定基準に適合しているか確認。
- 09:30
- 採掘現場状況の確認 採掘現場の図面作成のため、状況を確認する。
- 11:00
- 資料作成 許可申請書や報告会等の資料、データ等の取りまとめを行う。自分に課せられたテーマを進める。
- 12:00
- 昼食 昼食は独身寮のお弁当。
- 13:00
- 会議への参加 他部門と打ち合わせを実施する。
- 14:00
- 資料作成 午前中の作業の続き。
- 16:00
- 業者ダンプの依頼 現場主任と業者ダンプの台数について、打ち合わせて、業者へ連絡する。
- 16:30
- 資料作成
- 17:20
- 終業
- 23:00
- 就寝
Denkaを選んだ理由 自社の鉱山から原料調達できるという強み
クロロプレンゴムの世界シェアNo.1を誇るデンカ。しかも、通常石油系原料から作られるクロロプレンゴムを、自社の鉱山から調達可能な石灰石を原料として製造しているという点に、他社にはない競争力の高さを感じました。また、エネルギー源がほぼ0円である水力を生かした発電所を、自前で所有しているというところも魅力的でした。

応募者へのメッセージ 規模は小さくても将来性がある
全国各地に石灰石の採掘を行う会社はありますが、デンカのように自社で採掘した原料を幅広い製品に生かしている企業は少ないと思います。青海工場の原点は石灰石。セメント以外にクロロプレンゴムやカーバイド、特殊混和材など、石灰石を原料に多種多様な製品を製造しています。鉱山系の学生のみなさんはもちろん、将来性の高い会社で長く働きたい人にはぜひデンカを選んでほしいですね。