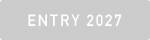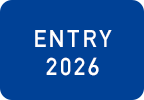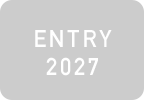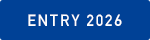
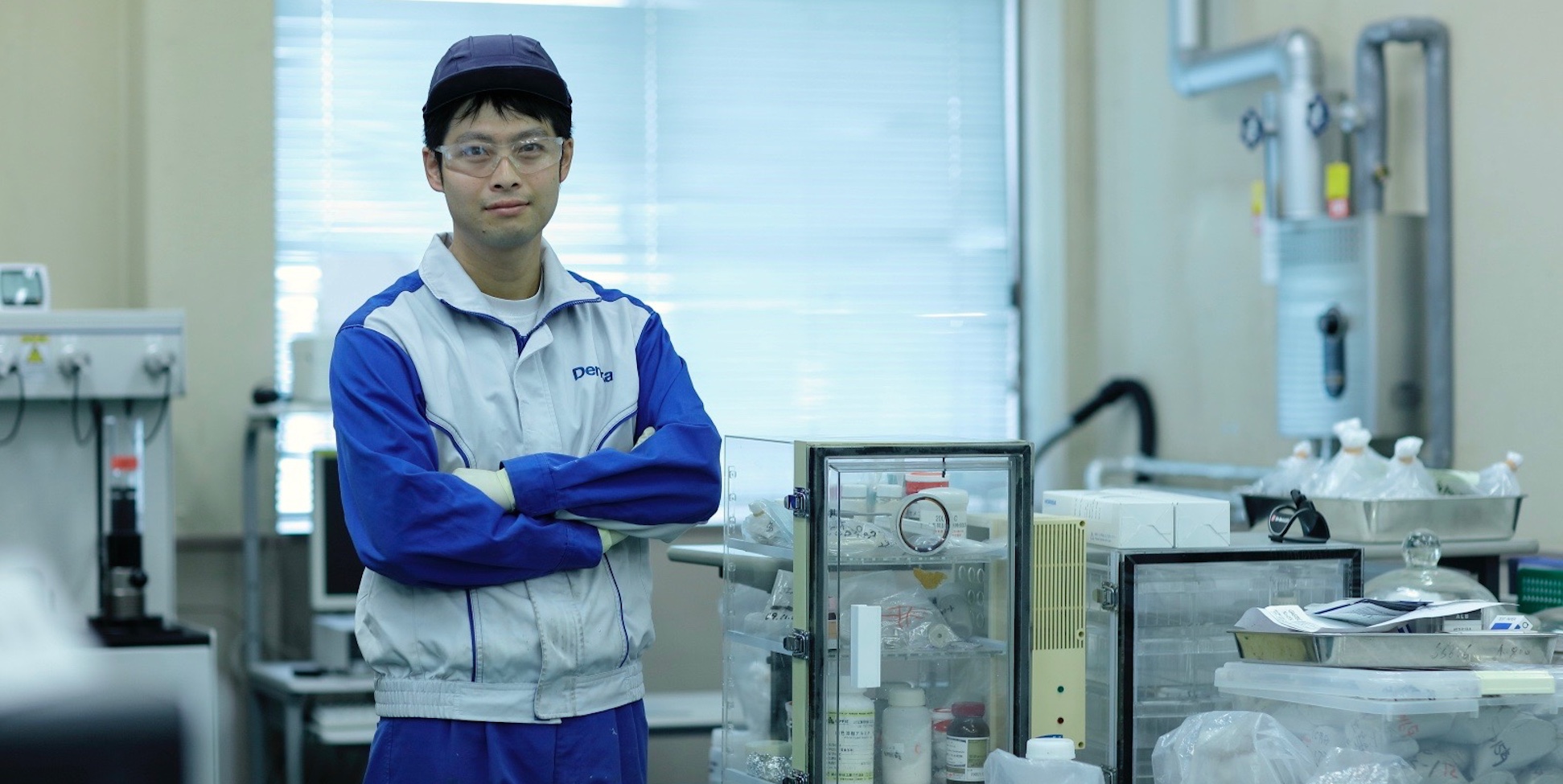
- JOB REVIEW
- 研究開発
現場の声に耳を傾け、
研究が果たす役割を考える。
- 宇城 将貴
- 青海工場 セメント・特混研究部
2013年入社
理工学研究科 材料工学専攻修了
※社員の所属部署・記事内容は取材当時のものです
多くの部門を介して
製品が供給できている
セメント・特混研究部に所属する宇城将貴は、自身の専門分野であるセメントという技術の奥深さについてこのように説明する。
「セメントの歴史は古く、古代ローマや中国にも建築にセメントが使われていました。歴史が長いだけあり、科学的な分析や考察も深いんです」
大学でセメント学の研究に打ち込んでいた宇城がデンカを知ったきっかけは、所属する研究室の教授だった。デンカのOBで、セメント・特殊混和材の研究に携わっていた人物だったのだ。
教授を通じて、デンカ社員と交流する機会を得た宇城は、就職活動でもデンカで働く自分をイメージし始める。
念願叶い、デンカに入社した宇城が配属されたのは青海工場での特殊混和材の研究開発の仕事だった。特殊混和材とはコンクリートに特殊な性能を付与する製品で、ひび割れ低減や高強度化、長寿命化など、用途に合わせて幅広いラインナップを揃えて、さまざま建設現場で利用されている。宇城は大学での研究を活かしながら、2年目からは自らが主体となって社外とのやり取りも行った。
「ドライミックスモルタルなど最終製品を製造している企業や、実際に工事を行うゼネコン、大学との共同研究など、社外とのつながりが非常に多いことに驚きました。同時に、社内では製造部や研究部、営業部など、お客様の元へ製品が届くまで多くの部門が関わり、安定して製品を供給できていることを改めて実感しました」

マーケットと研究をどうやってマッチさせるか
入社3年目に、宇城はマレーシアへの出張を言い渡された。デンカがマレーシアのドライミックスモルタルメーカーを買収したことをきっかけに、3カ月の期間、当該メーカーに駐在し、技術マーケティングを行う業務を任されたのである。現地メーカーの製品やマーケットを学ぶと共に、デンカの製品や技術がマレーシアで適用できるか検討する。お互いが持つ製品や技術を活用できる研究テーマやマーケットを探る狙いがあった。当然、会話は英語だ。
「ほぼ現地スタッフのみだったので、不慣れな英語で異なる分野の技術を理解したり、紹介したりするのは苦労しました。初めての海外出張だったので、文化や気候の違いにも戸惑いましたね」
気候の違いが特殊混和材の品質にも影響するなど、対話を重ねるうちに日本とマレーシアの違いが見えてきた。道路の補修など、マレーシアでは使われていない用途にも気づき、新たなマーケットを提案することもできた。
「建築分野から求められる性能値が日本とマレーシアで異なるため、何故この数値なのか、ニーズやマーケットに関する知見を深める必要がありました。研究や技術を市場とどうマッチさせるのか、改めて考えるきっかけになった3ヶ月でした」
この製品はどんな現場で、どんな規模でいくらコストをかけて使われるのか。研究が果たす役割を考えながら、現場の声を意識するようになった、と宇城は自分の成長を振り返る。

海外で「Denka」ブランドを高めたい
入社5年目の現在(※取材当時)、宇城は海外技術開発室に所属し、海外の現地ニーズや用途にマッチした製品開発や技術支援を行っている。中国、東南アジア、欧州、アメリカなどマーケットは多岐にわたり、国によって求められるものが異なるという。
「たとえばオーストラリア等の先進国では、重労働や悪環境での作業は嫌がられるため、粉塵が舞う中で粉体の製品を開袋投入する様な作業が必要な製品は受け入れられないという課題があります」
「現地の労働環境や風土に合わせて工程を見直したり、形状を粉末から液体に変えたり、言わば『ローカライズ』が必須ですが、これらは現地で実感しないと、その方向性が正確に理解できないと感じています」
今も2、3カ月に一度は海外に渡り、ニーズや評価方法などベストな製品を探っている宇城。建築物に高いクオリティが求められる国ほど、コンクリートに特性を付与できる特殊混和材の出番が増える。
「生活を支え、100年先も残り続ける物を生み出すことに、この分野の喜びがある」と宇城は話す。
「もっと海外でデンカの認知度を上げ、ブランド価値を高めたい。より専門知識やビジネスを学び、特殊混和材でデンカに貢献していきたい。そのためにもっと英語を磨き、海外とコミュニケーションを深めたいと思っています」
一日の仕事の流れ
- 07:20
- 起床
- 07:40
- 自宅を出発 通勤はマイカーで独身寮から移動。
- 08:00
- 会社に到着
- 08:30
- 部署全体ミーティング 部員全員でラジオ体操、KY(危険予知)の周知、出張報告、安全唱和を行います。そのあとは実験室の清掃をします。
- 08:40
- チームのミーティング グループのメンバーでミーティング。その日に行う作業の内容やKYについて共有します。
- 09:00
- 実験のセッティング開始 前日に計量し20℃に調整しておいた材料や型枠等を用意し、実験のセッティングを行います。
- 09:30
- モルタルやコンクリートの練混ぜを行い、型枠に打設して試料を作製します。
- 12:00
- 昼食
- 13:00
- 材齢処理 作製した試料の強度や長さ変化などの物性評価を行います。
- 14:00
- レポート作成 試験結果をレポートにまとめる。
- 15:00
- ミーティング グループで試験結果や考察、次のアクションについて報告し、今後の方向性について打ち合わせる。
- 16:00
- 論文・特許調査/作成 論文・特許を調べて最新の情報を取得したり、試験結果の考察を深めます。また、自身で論文や明細書を作成します。
- 17:20
- 終業
- 23:00
- 就寝
Denkaを選んだ理由 先輩社員の言葉が後押しに
大学で所属していた研究室の先生が、デンカのセメント・特殊混和材の研究部門の出身だったことがデンカを知ったきっかけです。その後、研究室の行事や学会を通じてセメント・特混に携わるデンカの社員とお話しする機会もありました。デンカの研究部は、若手もベテランも一人一人が主体となってテーマを進めており、会社にもそれを後押しする風土があることを感じたのが、入社を希望した理由です。

応募者へのメッセージ自分自身が主体となってテーマに携わる
デンカは、研究を通じてさまざまなことに挑戦し、自分自身がテーマの主体となって携われる風土の会社です。大変な部分もありますが、それ以上に達成感や充実感を得られます。仕事を通じて積極的に社会と交わり、貢献したい方にお勧めです。